4コーナー先頭から押し切る
古馬初対戦の3歳馬が殊勲
今ではJBC競走の意義となっている、生産者主導の競馬の祭典。かつて、この思いを抱く形で、1989年に創設されたレースが、ブリーダーズゴールドカップだった。JRAと地方馬の対決は、帝王賞に次ぐ歴史を持つ。しかし時を重ね、その格差が広がり、地方馬の出走が減っていき、2012年には地方馬が2頭のみ。しかも、地元馬が出走取消となり、浦和のトーセンスターンが唯一、地方馬として出走した。ホッカイドウ競馬で最も格式のあるレースで、さすがに危機感を覚えた主催者が、馬産地立脚の競馬であることから、牝馬の頂上決戦へ形を変えることを決意した。
JRAでも、父内国産限定の重賞だったカブトヤマ記念を福島牝馬ステークスに名称を変更。愛知杯とともに、04年から牝馬重賞へ移行している。そしてヴィクトリアマイルの創設(06年)が、牝馬路線整備の転機となった。競走馬のレベルが高くなり、馬産地保護の観点から、ブラックタイプ(牝系の系図で、重賞や準重賞の実績に応じてゴシック表記される)を充実できるようなレース創設へと、生産者の思いも変わっていく。このような背景から、ブリーダーズゴールドカップは2014年、南関東以外のダートグレードで唯一の古馬牝馬重賞に生まれ変わった。
昨年は、出走取消や競走除外が2頭あり8頭立てとなったが、枠順発表の段階で2桁の頭数は確保されるようになり、今年も12頭が出走。特に昨年、マルシュロレーヌがこのレースで楽々差し切りを決めた後、本場のブリーダーズカップ・ディスタフGIを制したことで、ブリーダーズゴールドカップJpnIIIの価値を上げた。JRA勢は補欠馬にも実績馬がいたほど、より関心が広がったと言える。
牝馬重賞となって以降、14年と21年以外は、その年の関東オークスJpnII優勝馬が挑戦し、18年のハービンマオ(5着)以外、いずれも馬券圏内に入っている。しかし、優勝した例はない。グレード別定で、JpnII勝ち馬は2キロ増となる。3歳馬にとってはその壁を打ち破ることの難しさにつながっていると思われる。グランブリッジは、そのジンクスに勝てるかどうか……。1つの焦点となった。
レースは、ブリンカー着用の地元馬であるノットイェットが思い切った逃げを打った。前半3ハロン35秒6、5ハロン60秒6と、不良馬場を意識したハイラップを刻んだ。さすがにノットイェットは3コーナーで失速。勝負どころからJRA勢の争いとなった。
ハイペースだったこともあり、最後の2ハロンは13秒0-13秒8と、タフなレースとなった。5ハロン標で先頭から0秒9差にいたグランブリッジは、3コーナーでハギノリュクスが先頭に立った時に仕掛け、4コーナーで早くも先頭に立つ。5ハロン標で1秒5差あったプリティーチャンスも、上がりを要する流れで大外から猛追。手に汗握る攻防の末、グランブリッジがクビ差で凌ぎ切った。
レース後、新谷功一調教師に話を伺うと、過去に3歳馬の優勝がなかったことを知っていた。厳しいレースになることを覚悟した中、環境の変化に配慮するため、早めに札幌競馬場へ移動し、当日輸送で挑んだ。馬体重も増え、前走以上の状態で挑むことができ、勝利という最高の結果を収めた。そして「JBCレディスクラシック」という言葉が、新谷調教師と福永騎手から聞かれた。同レースでの3歳馬の優勝は、15年のホワイトフーガ1頭のみ。ホワイトフーガは、同年のブリーダーズゴールドカップJpnIIIでは3着だった。古馬初対戦で解答を出したグランブリッジは、JBCレディスクラシックJpnIはもちろん、将来はマルシュロレーヌのように世界へ羽ばたく時を想像してしまう。
取材・文 古谷剛彦
写真 浅野一行(いちかんぽ)
Comment

新谷功一調教師
3歳馬には厳しいレースだというジンクスがあることはわかっていましたので、どれだけ耐えて走ってくれるか、不安もありました。環境の変化や不良馬場など、様々な課題をクリアし、この勝利はとても大きいと思います。詰めて使うタイプではないので、JBCレディスクラシックに直行したいと考えています。



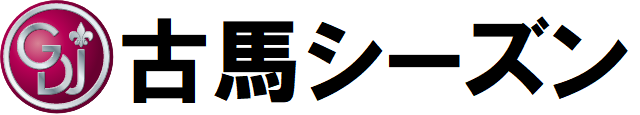




福永祐一騎手
すごく立ち回りが上手な馬で、砂を被る形でも問題なく、前走より状態も上がっていたと思います。仕掛けが早かった分、馬に負担をかけてしまいましたが、よく凌ぎ切ってくれました。同じ斤量で、古馬相手に勝ったことで、JBCレディスクラシックに向けて、自信を持って臨めると思います。