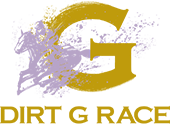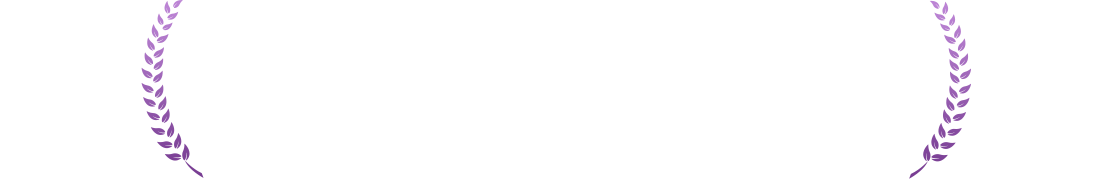屈辱の第1回ジャパンC、
痛感した“海外”との差
「シンザンを超えろ」を合い言葉に、日本の競馬関係者の間で「強い馬づくり」が強く意識されるようになったのは、1980年代のことだった。
81年に行われた日本初の国際競走ジャパンカップで、米国と加国から遠征してきた、それぞれの国では超一流とは認められていなかった馬たちが、上位4着まで独占。日本調教馬では、この年の秋に南関東から中央に転入したばかりだったゴールドスペンサーの5着が最先着で、直前の天皇賞・秋で1・2着していた当時の日本最強馬ホウヨウボーイとモンテプリンスは、いずれも掲示板にすら載ることが出来ないという結末に、関係者もファンも言葉をなくすほどの衝撃を受けた。
これをきっかけに、血統、馴致・育成、土壌や飼料など、競走馬を育てる上でのあらゆる側面を向上させるべく、関係者がたゆまぬ努力を積み重ねた結果、98年8月に仏国で、シーキングザパールがG1モーリスドゲスト賞(芝1300m)を、タイキシャトルがG1ジャックルマロワ賞(芝1600m)を制覇。翌99年にはエルコンドルパザーが、G1サンクルー大賞(芝2400m)を制した他、芝2400m路線の世界最高峰とされるG1凱旋門賞で2着に入る激走を見せた。
この3頭はいずれも米国産馬だったが、01年には日本産馬のステイゴールドが、G1香港ヴァーズ(芝2400m)に優勝。第1回ジャパンカップから20年の時を経て、日本で生産・育成されたサラブレッドが、海外G1制覇を果たすに至った。

20回目のG1挑戦となった01年香港ヴァーズで悲願のG1制覇を果たし、有終の美を飾ったステイゴールド。
中央・地方が一丸で
「ダートの強い馬づくり」
ご覧いただければ一目瞭然だが、この頃の日本馬による海外における良績は、芝のレースに特化している。
ダートの海外G1にトライしていなかったわけではなく、例えばG1ドバイワールドカップ(ダ2000m)には96年の第1回競走から、ほとんど毎年のように日本調教馬の参戦があった。だが、01年に2着に善戦したトゥザヴィクトリーを唯一の例外として、掲示板の確保も覚束ない状況が続いた。G1ケンタッキーダービー(ダ10F)やG1ブリーダーズカップクラシック(ダ10F)に挑んだ日本馬も、しかりである。
これには致し方のない背景があって、そもそもダート路線における「強い馬づくり」には、芝路線に比べて大きく立ち遅れた面があった。日本のクラシック体系は、競馬発祥の地・英国に倣ったものゆえ、主要競走の多くは芝が舞台で、日本の馬産も芝で強い馬を作ることを一義的な目的として、長く営まれてきた。
ダートにおける競走体系が整いはじめたのは90年代半ばで、具体的には、95年に中央地方指定交流競走が設けられたことが、大きなきっかけになったと筆者は見ている。そこから、中央と地方の関係者が意識を共有して、ダートにおける強い馬づくりに邁進しはじめたのだ。フェブラリーステークスがダート初のG1と認定されたのは、97年だった。

ダート初のG1となった97年フェブラリーステークス。シンコウウインディとストーンステッパーの叩き合いは、内のシンコウウインディに軍配が上がった。
すなわち、ダート路線における強い馬づくりは、芝路線に比べると20年近く遅れてようやく緒に就いたのである。
ダート競馬の未来を照らす
「二つの金字塔」
そう考えれば、ステイゴールドによるG1香港ヴァーズ制覇から20年後に、マルシュロレーヌによるG1ブリーダーズカップディスタフ制覇が達成されたというのは、決して遅すぎたわけではないのである。
いや、筆者の感覚からすると、むしろ「早かったな」というのが、偽らざる思いだ。
そう感じる理由は、二つある。
一つは、米国のダートと日本のダートでは、路面の質が異なる点がある。大きく括れば、日本のダートは砂で、アメリカのダートは土だ。能力が非常に高いという前提のもとに、米国のダートに適性のある個体を選別するのは、容易なことではないと考えていた。
もう一つは、勝ったレースがブリーダーズカップディスタフであったことだ。ブリーダーズカップディスタフは、芝2400m路線で言えば、凱旋門賞に相当するレースである。今や世界最強とも称される日本の芝中距離馬たちが、凱旋門賞を勝ちあぐねている間に、これに先んじて、牝馬限定のダート中距離戦線では世界最高峰に位置するレースを手中にしたのだ。
日本競馬史における、屈指の大快挙であることは間違いない。

世界最高峰のBCディスタフを制したマルシュロレーヌの功績は、日本のダート競走の地位を大いに高めたと言っても過言ではない。
くしくも同年、Jpn1JBCクラシックをミューチャリー(牡5)が制し、地方所属馬としての初優勝を果たした。ダート競馬を舞台に、二つの金字塔が相次いで打ち立てられたことで、我が国のダート競馬が益々活性化していくことが期待される。

船橋所属のミューチャリーが、地方所属馬として史上初となるJBCクラシック制覇の快挙を果たした。
そして、日本の馬産地におけるダート血脈も価値も、近年はうなぎ登りである。
ダート路線における強い馬づくりは、今後、目に見えて加速していくことになりそうだ。
2022年2月10日掲載

合田直弘 Goda Naohiro
1959年(昭和34年)東京に生まれ。父親が競馬ファンで、週末の午後は必ず茶の間のテレビが競馬中継を映す家庭で育つ。1982年(昭和57年)大学を卒業しテレビ東京に入社。営業局勤務を経てスポーツ局に異動し競馬中継の製作に携わり、1988年(昭和63年)テレビ東京を退社。その後イギリスにて海外競馬に学ぶ日々を過ごし、同年、日本国外の競馬関連業務を行う有限会社「リージェント」を設立。同時期にテレビ・新聞などで解説を始め現在に至る。